
4月(場合によっては9月)は年度の移り変わりで学生や社会人等は、一人暮らしを始めたりする人も多い。
また、結婚して初めてアパートやマンションに住む事もあるだろう。
特に女性の一人暮らしは、いろいろ危険な事も多いので慎重に選んだ方がいい。
以下は、そういった人達の参考になるかもしれない。
注 意
あくまでも参考であり、該当しない物件は即、悪い物件というわけではない事を承知の上で以下を読むこと。
また全て個人の責任において判断すること。このサイトはいかなる保証もしません。
(逆に以下の条件を全てクリアする物件は少ないかも...)
- 基本的には1人1部屋、2人なら2部屋必要であるが、子供が出来る予定でしばらくそこに住むならば3部屋にしておいた方がいい事もある。
広めのロフトがあったり、1ルームでも仕切って使えるほど広かったりすると条件が変わる事もたまにある。
- 不動産屋を選ぶ。
応対が悪いとか、評判の悪い所は避ける。
なぜか自分の意志と違って別の物件にしようとするところも多い。
「ここらへんの物件だと、どこでもこれぐらいの金額になりますけど」と言われる事もあるがそうでないことも多い。
- 部屋の間取り図だけで契約してはいけない。
当然の話だが、面倒とか時間がないからと図面だけで決めるより、自分の目で実際にじっくり見てきめるべきである。
- いろいろな物件を見て納得のいく物件を選ぶ。
何度が断るとなんとなくそろそろ妥協しようかと思いがちだが、やはり納得がいく物件がみつかるまで同じ不動産屋でもねばったほうがいい。
「この物件は人気ですぐに他の人に取られてしまいますよ」に惑わされないように冷静な判断をすること。
また、部屋の感じだけ見て決める人もいるが、逆に設備等の細かい所をチェックする。
入居してから意外と問題になる壁や床の音の伝わり具合も調べる。
フローリングは特に音が響くので注意。
なんとなくで妥協して結局苦しむのは自分である。
- よくいわれるが南向きがいい。
やはり部屋の窓から日差しが入る方が気分的にもいい。
できれば風通しがいいことも加えたい。
間取り図でも窓から窓へなるべく壁にぶつかることなく、直線が引けるとよい。(玄関はとりあえず除く)
例えば、部屋から台所の窓から窓へ風が一直線に抜ける様な部屋ならベストである。
洗面所や風呂場に窓や換気口があると湿気の面でもよい。
- 昼と夜では、全く雰囲気が違う。
ただ単に暗くなるだけじゃないかなんて思うんだけど実際はかなり違っている。
特に駅やバス停からの夜道はかなり変化することが多い。
痴漢やストーカー等を考えると、ちょっと遠い場合でも大通りや人通りのなるべく多い明るい道で行けるほうがよい。
しかし、大通り沿いは逆に夜になると運搬トラックがうるさいところもある。
やはり自分の目で確認しておいたほうがいい。
- 2階以上の場合、ベランダもよく見る。
全く使わない人はいいが、布団を干したり、ちょっと観葉植物を置いたりして楽しみたい人には大事な場所である。
まず、ベランダは外側から底を見る。
アパートの場合、意外と鉄板1枚の様な床だったり、めくれてたり、さびてぼろぼろだったりもする。
もっと恐いところは建物の壁からかなり隙間ができて外れそうなベランダも本当にある。
- 外に共同のブレーカーがある場合は、結構いたずらされることも多い。
パソコンを使っている場合は壊れる可能性が高いので避けた方がいい。
- ガスの種類もいろいろある。
LPガス、都市ガス等、まあ気分的好みかもしれない。
- ガスの給湯機はベランダにあるほうがいい。
玄関側にあるといたずらされることもある。
新聞勧誘員に、断られた腹いせに栓を止められた人もいる。
- 連帯保証人の要らないところは、やはり保証もない。
たまに親の同意が得られないからとかで選ぶ人もいるが、気をつけたほうがいい。
当然いい人達もいるし、そうでない人もいるかもしれない。
- 車を持っていないなら、駐車場のないところの方がいい。
すぐ目の前が駐車場の場合、階によっては意外と車のアイドリングの音がうるさい。
特に寝ているときはかなり気になるものである。
自分も持っているならばお互い様で割り切れるかも(?)しれないが持ってない場合は迷惑以外の何物でもない。
もっと最悪なのは、そのアパートやマンションの駐車場でない別の広い駐車場が隣にあったりすると夜中に溜まり場になってうるさいこともある。
- そこに住んでる住民を把握する。
やはり住民とは間接的でも関連してくる。
隣がうるさいとか、子供がうるさいとか。
ある程度は把握して自分と近い層の人達が住む場所を選んだ方がいい。
駐車場にある車でどんな人が住んでいるかなんとなく把握できる場合もある。
- 防犯的に危ないところは避ける。
あたりまえの事だが、意外にこれは見逃している点も多い。
普通は2階以上がいいとされている。
特に女性の一人暮らしなら下着泥棒やのぞき、空き巣、場合によってはストーカー等の被害を考えればそう思えるがそう単純でもない。
屋上や電信柱、隣の家の屋根伝い等、思わぬ所から侵入される事もあるので注意する。
オートロックは基本的にセキュリティが高いが完全ではないし、油断するので注意。
周りの状況も含めてよく建物を観察し、安全性を必ず確認すること。
- ペット可でなければ当然飼ってはいけない。
みつかった場合は、即退去ということも。
- 楽器可でなければ音を出して演奏できない。
演奏の上手下手に関係なく騒音として扱われる。
- 現状維持で返すことを前提とする。
要するに元へ戻さなくてはならない。
穴を開けたり、工事したりする場合は持ち主の許可が必ず必要であり、元へ戻さなくてもOKなわけではない。
エアコンがなくて取り付けた場合、壁に穴を開けて室外機と太い管を接続する。
そのための許可はまず出るが、その家を明け渡すときに次の人も使えるようにそのままか、元へ戻すかは持ち主が決めるので自分で勝手に決めてはいけない。
基本的に、くぎ1本打てないつもりで考える。
その意味では設備が整っているほうがいい。
- 新築にこだわるか
新築にこだわる人も多いが、古くても出来のいいマンションもある。
新築でも出来の悪い場合、アレルギーになる原因の1つとも言われているホルムアルデヒド(壁紙の接着剤等に含まれる)臭いところもある。
要は建物の出来・不出来かもしれない。
- 毎月の出費を考える。
特に初めての場合、「家賃+電気+ガス+水道+電話代+雑費+小遣い」と考えてしまう人もなぜか多い。
意外にかかるのに忘れてしまうのは食費である。
基本的に自分で料理したほうが1ヶ月で、栄養バランスもとれて安くなる。(計画的でないとそうでもなくなる)
最近はコンビニでも栄養バランスが考えられている食品も多い。
1食500円(例えば)としても1日3食で1ヶ月約30日と計算しても 4万5千円 である。
ちょっとお茶したり、ちょっと飲みにいったりすると 5、6万は軽く超えてしまう。
月の固定収入額の3分の1が家賃の目安といわれるが、少しでも貯金できる計画でいないとならない。
- 契約書はよく読む。絶対熟読する。
何かトラブルが発生したとき、場合によってはこれが味方になったり敵になったりする。
できれば1日家に帰ってじっくり読む。
他の人にも読んでもらって自分にいいように解釈したり、誤解のないようにする。
不動産屋は「まあ形式的なものですから」というがそうでないことも多い。
「管理人は宅急便の荷物等を受け取ったら個人の玄関を開けて荷物を入れておく」なんてところもある。
他に石油ストーブ使用不可等、出来る事、出来ない事も書かれている。
- 借地借家法が2000年3月1日に改正された。
しかし現在は、以前の借家法と新しい借家法の両方が混在している。
それをどちらかに決めるのはその建物の持ち主が決めるが、全てに新しい借家法が適用されるわけではない。
しかも契約時に口頭でなく書面でないと無効のはずである。
新しい借家法では、基本的に立ち退きをさせやすい法律となっている。
法律関係は重要なのできちんと正式な所で調べ、不動産屋ともよく話し合うこと。
- 入居するときはかなりの出費が必要となる。
敷金2ヶ月、礼金2ヶ月の場合、最初の支払いは少なくとも家賃×5は必要となる。
(管理費もあるところはそれも払う。その他に、来月分の家賃必須のときもある)
でもそれだけじゃない。
引越し代や、生活に必要な電気製品、家具、雑貨を買ったりと出費が多い。
電話機も差し込むコンセントが既にあるからOKではない。
いわば自分の電話番号を買わなければならない。
加入料は8万弱である。
PHSや携帯電話という方法もあるが、初めての一人暮らしの場合は意外と電話代がかかってしまう事も多い。
加えて火災保険も必須である。きちんと証書を受け取ること。
これがないと火事になった場合大問題になるが、実際火事になることは少ないので料金だけ取るインチキな所もある。
その他に鍵は前の人が使ってた物と交換してないので、交換したいときは料金がかかる。
気になる人は交換したほうがいい。
- 住宅金融公庫で借りて建てられたアパートやマンションで返済中の物件は、実は礼金や更新料をとってはいけない。
敷金は徴収できるが他は徴収できない規則になっている。
実際は無視されていることや、不動産屋もよく把握していないことも多い。
既に払ってしまった人も違反している場合は戻ってくる可能性が高い。
詳細は、住宅金融公庫のサイトへ
当然、これだけでは足りない可能性や場所によって異なる事があるので、よく調べたほうがいい。
特に法律関係は改正されることもあるので注意が必要である。
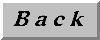
[an error occurred while processing this directive]
