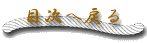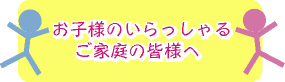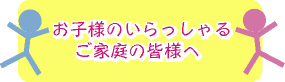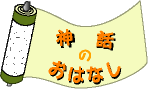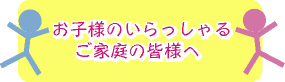
抜粋 宮城県神社庁 監修 平成十一年度 祭事暦より
私たち日本人はお祭好きと、よく言われます。
しかしその由来などについて本当に正しく理解されているでしょうか?
「神社の祭り」 時代や生活がかわっても遥かなる祖先から受継いできた、
私たちの町や村のかかわりや、美しい四季の風景や私たちの営みに思いを馳せ、
今生きている歴史や風土をこれからも大切にしていきませんか?
以下は、日本という国のはじまりの神話です。お子様にもぜひ読んであげてください。
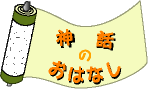
|

|
しんわと いうのは、とおい むかしから つたわってきた かみさまの おはなしです。
にほんの しんわを よんでむかし むかしの にっぽんの すがたを おもい うかべましょう。
|
|

じめんが まだ うまれたばかりで、みずに ういた あぶらの ように ふわふわ していたころ、そらの うえの たかい たかい ところから、じめんを かためて よいくにを つくるため、ちじょうを みおろしている おとこと おんなの かみさまが いらっしゃいました。
おなまえは いざなぎのみこと と いざなみのみこと。おふたりは、じめんを かためて くにを つくるため ながい ほこを うみに さしこみ、ころころと かきまわしました。
すると どうでしょう。 ほこの さきから おちる かいすいが、みるみる うちに つもり、しまが できたでは ありませんか。
これを ごらんになった おふたりは とてもよろこび、このしまに おり、けっこんなさいました。そして つぎつぎに しまを おうみになりました。
しこく、ほんしゅう、きゅうしゅう、など。にっぽんの くには このようにして うまれたのです。
|
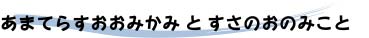
いざなぎのみこと と いざなみのみことの みこに あまてらすおおみかみという、やさしい おねえさまの かみさまと、 すさのうのみこと という、げんきな おとうとの かみさまが いらっしゃいました。
しかし、すさのおのみことは らんぼうな かみさまで あまてらすおおみかみを こまらせてばかり。 ついに とおくに おいやられて しまいました。
こうして、すさのうのみことが ひとり いずものくにを あるいていかれると、ひとりの むすめが おとうさん おかあさんと ないていました。
わけをきくと、もうすぐ、あたまが やっつもある だいじゃ 「やまたのおろち」が むすめを たべに やってくると いうではありませんか。
すさのおのみことは、すぐに いえの まわりに かきねを つくらせ、その まわりに おさけを いれた おおきな かめを やっつ おかせました。
しばらくすると、きゅうに あたりが くらくなり、だいじゃが あらわれました。だいじゃは それは それは おそろしい すがたで、やっつの あたまには ぎらぎらと まっかな めが ひかっていました。
そして かめを みつけると、いきおいよく おさけを のみだし、しばらくすると、よって ねむって しまいました。
すさのおのみことは、ゆうきを ふりしぼって、つるぎで だいじゃに きりかかりました。きがついた だいじゃは、みことめがけてとびかかってきます。
しかし、みことは おそいかかる だいじゃを つぎつぎに きりたおして、ついに たいじして しまいました。
すさのおのみことは、たすけたむすめ、くしなだひめと けっこんされ、しあわせに くらされたと いうことです。
|
|