| 「人工肛門」と「洗腸」について |
なぜ人工肛門に
|
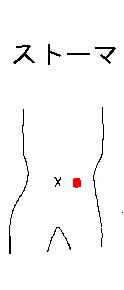 |
人工肛門となった人はどのように対応しているのでしょうか
- 切除した範囲、部位によって大きく異なります。
- 基本的には意志とは無関係に排泄される便を受け溜めるための「パウチ」と呼ばれる樹脂製の袋を排泄口(ストーマ)に貼付しておき、便が溜まったら取り替えるという方法です。つまりパウチが便を溜める直腸の代わりをつとめるわけです。これにはいくつかの問題があります。
- 便の溜まった袋をつけていると行動に多かれ少なかれ制約を受けざるを得ません
- 貼付剤(接着剤)を使うので、個人差もありますが肌への影響(かぶれ、ただれ等)を受けます
- ときにはパウチ剥がれなどによる便の洩れ、匂いなどのトラブルも起こります
- 洗腸での対応
- 簡単に言えば大がかりな浣腸のようなものです。大腸の中の残滓物を強制的に流し出してしまい、排便をある程度の時間押さえようという方法です
- この方法をとれる人は、切除した後の大腸の残りが比較的多い人に限られます。原因として一番多い直腸癌の場合には、切除するのはS状結腸あたりまでですから、残される部分は多くなります。したがって洗腸で対応することがが可能です。洗腸対応が可能かどうかは医師の指示によります。
- 洗腸のメリットは大きくて、個人差はあるのの、通常これで24時間から48時間次の排便まで間があきます。普通の人とほとんど変わらない生活が可能になってくるわけです。
- しかしこれは医療行為に近い作業で、ひとつ誤ると事故にもなりかねません。私もこの作業を急いだ時、貧血、失神してしまったこがありました。
- 切除後の大腸の残りが少ないケースでは、洗腸はできません。このため生涯パウチを貼っていなければなりません。こうした方の日常の苦労は推し量ることが出来ないほどのものがあります。
- 私の場合はS状結腸までの切除ですんだため、洗腸で対処できます。いろいろ問題がないわけではありませんが、ジョギングや登山ができるのも洗腸ができるおかげです。
- 洗腸とは
- 体温ほどの温湯を水圧を利用して排泄口(ストーマ)から大腸内へ注入します。量は私の場合で約900CCです。
- 注入した温湯が漏れ出さないよう、ストーマを押さえてしばらく待ちます。
- すると大腸内で温湯と残滓物(便)がまじりあいながら、排泄しようとする圧が高まってきます。押さえていたストーマの口を開けてやると排泄がはじまります。
- 個人差はありますが、排出が始まって30から40分前後でほぼ出終わります。
- これで大腸内はほぼ空っぽになり、次の便が排泄口までたどりつくまでの時間稼ぎができるということになります。
- すべての作業の所要時間は私の場合1時間ないし1時間20分ほどかかります。
- その他
- 洗腸で100%安心はできません。
- トラブルは常につきまといます。生身の体ですから下痢その他の体の変調はいつでも起こり得ます。洗腸ができたとしてもやはり行動への制約は拭い去ることはできないのです。
- つくられた人工肛門(ストーマ)そのものにも、種々の問題が発生し、それに悩まされる人たちも数多くいます。
- また手術による神経損傷で、排尿障害(出にくくなる)や性機能障害(勃起不能、射精不能)などを起こすケースも多くこれも問題の一つです。
|
このほかに膀胱癌などによって「人工膀胱」となる人もいます。社会活動への適応が一層厳しいものとなります。
人工肛門、人工膀胱となった人々(両者をあわせてオストメイトと呼びます)で組織された「オストミー協会」、あるいはパウチ等の装具を販売する会社が運営する「明るい暮らしの会」、あるいは病院単位の患者会というようなものがあり、オストメイト同士がノウハウを交換したり、悩みを語ったり、お互いに励ましあいながら生きています。(戻る)
|