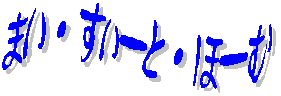
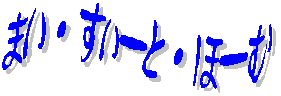
![]()
その日四月十五日は、火村英生の誕生日だった。
彼と、SF作家の有栖川有栖は、誕生日を祝うため、京都は河原町にある海鮮レストランで、食事を済ませ、今はパブ【ジャックダニエル】に場所をうつしている。
さきにレストランで、満腹になっている二人は、カウンターに並んで座り、静かに店と同じ名のウイスキーを、ロックで飲んでいた。
よく喋り、よく飲んだ。くつろいだ気分で、火村はこの後の予定を考えて頬がほころびそうになるのを押さえている。
火村は、ここからバスで、一五分ほどのところに下宿していたが、今日はそこへは帰らない。四条駅近くのシティホテルを予約しているのだ。
誕生日くらいは少しだけ、贅沢をしてもいいだろう。日頃に彼はかなり質素倹約に励んでいるのだ。どうしても、お金をためて欲しいものがあるから。
「火村、何をニヤケてるんや?」
アリスが揶揄するように問う。
「別に。ただちょっとここのところ働き過ぎだったからな、久しぶりにゆっくり出来て、嬉しいだけだ」
「ふ〜ん」
全然そんな言葉は信じてないぞ、という顔で、アリスはナッツを放り投げて口でキャッチ・・・・・し損ねた。
当然、床にこぼ落ちるはずのアーモンドは、しかし、床の寸前で落下を停止し、あっと言う間に火村の手の中におさまった。
「行儀の悪い奴だな」
とだけ言って、自分の口に放り込む。
アリスは目を剥いた。
「アホ!こんなところでそんなことするな。誰かに見られたらどないするつもりや」
言いながら周囲の人々の様子を窺う。
スツールひとつあけて座っているカップルは、お互いのことしか見えていないようだし、後ろのテーブル席の四人連れの女性達は、自分たちのお喋りに夢中で、こちらのことを見ていた気配はない。
誰も見ていなかったようだと確認して、ようやくほっとする。
「アリス、あんまり気にし過ぎだぜ、大丈夫だ。ちゃんと状況くらい考えてるんだから」
アリスの投げたアーモンドが、落下を免れたのは、手品でもなければ見間違いということもない。火村が、やったことだった。
「そない言うても、どこで誰が見てるか知れへんのや、つまらないことに使うなや」
そこへ、いきなりけたたましい音が鳴り始めた。
「クソッ、仕事かよ」
ポケットベルを止め、表示された電話番号を見ながら火村が舌打ちした。
「仕事をシャットアウトしたいのやったら、電源切っといたらええやないか」
アリスは、不満を隠そうともせずに、ふくれている。
締切は明日だったのに、火村の誕生日のために三日間も徹夜して、昨日のうちに脱稿してきたのだ。それが、当人の仕事で邪魔されるなど、あまりに腹立たしい。
「そう、怒るなよ。ここからの依頼は外せねぇんだ。なんせコレのいい仕事ばかりだからな」
火村は、親指と人差し指で、輪っかを作ってウインクした。
「守銭奴」
「それもこれも、防音設備完備の高級マンションのため。ひいては俺達のスイートホームのためじゃねぇか。なるべく早く片付けて行くから、おまえ先にホテルに行っててくれよ」
「俺は別に、防音設備なんていらないんやからな。俺達なんて言って俺までまぜることはないやろ」
「あの時にどんな大声出してもOKなんだぞ、おまえだって嬉しいだろ」
「アホ!」
火村は、怒っているアリスを置き去りにして店を出て行った。
火村英生はサイキックだった。その能力をいかした【仕事】をしている。アリスは、自分の小説のネタにはしないという約束で、火村の活躍した話をよく聴かせてもらっている。
火村が、防音設備を必要とするのは、彼の能力と関係している。本当にあの時の声の用心のためなどではなかった。彼が、本当に安らいだ時間を手に入れるためには、完全防音の部屋が必要なのだった。
彼は、物体を手を使わずに動かせるだけでなく、聴覚が人の数倍敏感に生まれついている。元気な時には、自己制御出来るので、音にわずらわされることはない。だが、体力を消耗している時には、神経が過敏になってしまい、小さな音さえ気になってしまうのだ。
そうなると、よほど別のことに意識を集中させない限り、音が耐えられないほどの苦痛になる。
超能力者は、決して万能ではない。彼には彼の悩みがあり、そのせいで、アリスにどれだけ守銭奴と罵られようと、お仕事に励まなければならないのだった。
指示のあった現場は、彼等が飲んでいた場所から徒歩数分。大通りのファッション関係のショップが立ち並ぶビルの前だった。
ガラス張りのそのビルの、ガラスの大半が砕け散っていた。
野次馬が、幾重にも取り巻いて、もともと人混みなのが、いつもの数倍に膨れ上がっている。
そして、その中心に青く発光するものが見える。
怒号と悲鳴。ガラスの炸裂音が響く。
どうやらビルの中の洋服のディスプレイや、棚なども、なぎ倒されているらしい。
怪我人が出たらしく、遠く救急車のサイレンも聞こえてきた。
「危ないから、下がってください!」
などと、叫ぶ警察官の声も虚しく、人々は既にパニック状態に陥っている。
火村は悠然と人混みをかきわけて前に出る。
いや、実際はかきわけているわけではなかった。
ここまでパニックになった人々の視線など気にする必要はない。障害物は、すべて能力で排除しながら進んで行った。
騒ぎの中心にいたのは、小さな女の子だった。
ピンクのフリルのついたワンピースを着て、髪には真っ赤なリボンがふたつ。まだ、三つか四つ、幼児と呼ぶべき年齢だろう。
その子の、全身が青く光っているのだ。
大きな瞳は焦点があっていない。突然起きた自己の超能力の暴走に為す術もなく意識を手放してしまっている。
明らかに、この騒ぎを引き起こしたのは、彼女だった。
(また、こんな子供かよ)
火村は、内心でつぶやいた。今月に入ってからだけでも、もう三件目だった。それも、この子と同じくらいの幼児ばかりが引き起こす惨事が続いている。
超能力を持って生まれる人間は、それほど多くはない。だが、確かに存在する。そして、その能力の発動には個人差がある。火村の場合は幼い頃から徐々にその力が増幅してきたので、完全に自分でコントロール出来る。だが、何かのきっかけで、唐突に能力が発動する者もいる。その勢いが急激であるほど、その者は自分自身でその力をコントロール出来ない場合が多い。力が暴走した揚げ句、多くの人を巻き込む大事故を引き起こしたり、精神がそれに耐えきれずに発狂してしまうこともある。
火村は、引き留めようとする警官を制して、少女の腕を掴んだ。
猛烈なパワーが、身体に流れ込んできて、感電したような感覚におそわれる。
気を引き締めてかからなければ危険だ。
彼女のパワーに押し切られ、引きずられる。
だが全力でかかれば、このくらいならなんとかなる。
火村の完成したサイキックが、少女のそれをなだめ、押しとどめる。精神を右手のひらに集中し、彼女の額にあてた。
彼女の身体から、少しづつ光が失われてゆく。
それとともに、その瞳に正気の色が戻る。
「大丈夫。なんともない。君のせいじゃないから、安心して」
火村は少女の頭をなでながら、繰り返す。
アリスが見たら驚きそうなほど、日頃の彼からは想像もつかないような、優しい声だった。
少女は、その言葉を理解したものか、ガラスの炸裂や、ビルの内部の破壊はやんでいた。
いつの間にか静まりかえった人々は、息を殺してこの様子を見守っていた。
火村は、警官に少女を渡して、素早く立ち去った。
後のことは、依頼主が雇った別のエスパーの仕事だ。
野次馬達から、今の火村と少女の記憶を消す。集団であればあるほど、それは難しいことではないらしい。
火村は人混みを抜けると、立ち止まって肩で息をついた。
「また、無茶をしたんやないのか?」
やんわりと、責めるような口調で話しかけられ顔をあげると目の前にアリスの顔があった。
心配そうに火村を見ながら、わきに手をかける。
「先に、行ったんじゃなかったのか?」
「おまえが、【仕事】のあとにどんだけ消耗するかは解ってる。とにかく肩につかまれよ。今日はもう、帰った方がええんやないか?」
火村は、きっぱりと首を振る。
「いいや、今日は誕生日だぜ。俺は絶対、おまえとホテルに行く!」
アリスは、赤くなってまたきょろきょろと周囲を見渡した。
「アホ!そんなでかい声で何ぬかす」
怒りながらも、諦めたようにタクシーを呼び止めた。
歩いても、たいした距離ではないのだが、疲労困憊いちじるしい火村にはかなりしんどい距離だろう。
「どうせ、眠るだけなんやから、どこでも一緒やのになぁ」
アリスは、不服そうに呟く。
「誰が眠るだけなんだよ、そうはいかないからな」
火村は、能力を使い切り消耗しきっていながらも、口だけは元気なようだった。
ようやく辿り着いたホテルの一室。
火村は、アリスの腰に両腕をまわし膝に頭をのせて、今にも眠ってしまいそうな体勢である。
「だから、無理しないで、眠ったらええのに」
溜息まじりのアリスの呟きは、火村の耳には届かなかった。
「また、子供だった」
火村は、先刻の少女のことを考えていた。
アリスは、自分の膝につっぷしている火村の髪を梳きながら訊く。
「能力が発動するきっかけ、なんてゆうのは、そう簡単にそこらに転がってるもんやないやろ?」
「ああ。こうもたて続くと、偶然じゃねぇだろうな。誰かがわざと能力の未発動者、特に暴発したらコントロールがきかない小さい子供をターゲットにやってることだ」
心当たりがあるような火村の口ぶりに、アリスは眉をあげる。
「そんなことが作為的に出来るんか?」
「俺には出来ねぇよ。だけど、超能力の種類なんて、まだはっきり限定出来ないってのが現状なんだ。他人の潜在能力を引き出す力を持つ者の存在は否定できないぜ」
「だったら、そいつを捕まえれば、この騒ぎは収まるわけやないか?」
「そうだな。だけど、当事者の子供には可哀想だが、ここのところ、おかげで実入りがいいのも確かだからな。どうせそいつを狩るのだったら、マンション手に入れてからにする」
火村は、顔をあげアリスにニヤリと笑ってみせた。
アリスは、火村の頭をポコリとはたいた。
「不謹慎やな。まさかおまえがやらせてるわけやないやろうな?」
彼の仕事熱心さを思うと、あり得ない話でもないような気がしてきてアリスは疑りの眼差しを向ける。
「人聞きの悪いことを言うなよ。俺、そこまで悪党じゃねぇよ」
心外そうな声だった。
「今度はポケベルの電源も切ったし、機嫌なおせよ、な」
たった今、ポケベルがなったとしても火村は使いモノにならないのだ。サイキックの能力は無尽蔵ではないのだから。
「当たり前やろ、もう眠る寸前なんやから」
火村は心底情けないような顔で、アリスを見つめた。
アリスも笑って見つめ返す。
「別に機嫌が悪いわけやないよ。お疲れさま。おまえのおかげで女の子一人助かったやないか。今日はそれでよしとしとけや、おやすみ」
火村は、何か言いたそうな顔をしたが、気力はもう限界だった。
少女の暴走した力を押さえるのには、本人が自覚していた以上に能力を消耗していた。
火村はそのままアリスの膝につっぷして、寝息をたてはじめた。
アリスはしばらくその寝顔をながめていた。
差別も迫害も恐れずに、己の宿命に前向きな男。
誰よりも、繊細な耳を持ち、仕事の後には音に苦しむことが常なのだが、アリスを抱きしめていれば何故かぐっすり眠れるのだという。
「これじゃ俺、テディベアみたいやないか」
ぬいぐるみを抱いてないと眠れない女の子みたいだぜ火村。と、考えて苦笑する。
強い潜在能力を見分け、その発動を促す力を持つという。そんな存在と直接対決しなければならなくなったら、火村はもっと消耗し、ボロボロに傷ついてしまうかも知れない。
それでもアリスには、どうすることも出来ない。
アリスには、小石一つ動かす能力もないのだから。
「だけど火村、おまえは疲れた時はいつもおまえのテディベアやったるからな。負けるんやないぞ」
熟睡してしまった男に聞こえるはずもないのが解っていて、アリスは囁く。
「誕生日おめでとう」
そして、額にそっとキスをおとした
翌朝。すっかり復調した火村は、仏頂面で、ベッドにあぐらをかいている。
「なんで、起こしてくれないんだよ。せっかくこんな部屋に泊まっても寝てただけだなんて、贅沢過ぎなんだよ、勿体ねぇだろう!」
「うるさい。俺やって、一晩中膝枕して妙な体勢で寝たせいで身体が痛いんや。おまえの誕生日やと思って耐えてやったんやから、そない文句言わんでもええやろ!」
アリスもひく気はなかった。
「よし、解った。時間延長だ。な、アリス」
火村は、アリスの肩を抱き寄せる。
「アホ!おまえが寝てるうちに精算済ませてきたわ、寝惚けたこと言うな。帰るぞ」
こうなったら、バリバリ働いて一日も早く二人のスイートホームを手に入れてやる!と、火村は拳を固めて心に誓うだった。
《fin.》