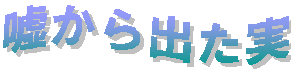
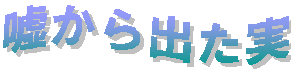
俺の下宿にアリスが遊びに来ていた時のことだ。何気なく見ていたテレビのニュース番組で、レポーターを募集するという。 それも、年齢制限がやたらと幅広い。30歳から60歳だと言うのだ。脱サラ組大歓迎ということで、何のレポートをしたいかという企画を原稿用紙に10枚程度、それから写真をテレビ局へ送付することで応募出来るらしい。
「なぁ、あの年俸なら、先生よりずっとええんやないか?」
枝豆を口に放り込みつつ、アリスが呑気に感想を述べた。
確かに、教授になってしまえば、あれよりもずっともらえるだろうが、助教授の給料などたかが知れている。
「だからって、俺が応募したら受かるに決まってるから悪いだろ」
当然のことを言った俺に、アリスは呆れたような目を向けた。
「たいした自信やな」
「写真を送れってことは、それなりの容姿を期待してのことだろうし、レポートくらい書き慣れてるんだぜ。反則だ。真面目に第二の人生やり直したいって考えてるおっさんたちに失礼じゃねぇか」
だが、アリスはそれを笑い飛ばした。
「火村、おまえには無理や。どうせ応募しても通るわけないわ。賭けてもええよ」
「何を賭ける?」
「そうやな。俺が勝ったら、今度の締切前に一週間、俺の夕飯係な」
毎日講義が終わったら大阪に直行しろってことか。一週間。会えるのは嬉しいが、締切前ってことは、夕飯作ったらさっさと帰れってことじゃないか。
「よし。じゃあ、俺が勝ったらおまえのおごりで旅行だ。土日で行ける場所にまけといてやるぜ」
売り言葉に買い言葉だった。
俺はアリスとの旅行を楽しみに、せっせとレポートを書き、今までで一番写りのいい写真をテレビ局に送った。
それで通った場合、本気で大学を辞める気なのか? 別に、そこまで真剣に考えていたわけではない。だいたい、その仕事が大学の片手間で出来ないとは限らないのだから、選ばれた時にはその時に考えればいいことだろう。
結果、第一次選考を通り、面接に行くことになった。
「嘘から出た実ってわけだな。明日、東京で面接なんだ」
電話でそう報告した俺に、アリスはまだまだ余裕の口調だった。
『第一次の選考が通ったくらいで、喜ぶのは早いわ。写真は喋れへんからな』
「おまえ、俺が喋ったら本性がバレるとでも言いたいのか?」
『ああ、よう解ってるやんか』
俺は、そこまで言われて、意地になった。 こうなったら、何が何でも、レポーターになって、アリスに旅行をプレゼントさせてやるんだ!
面接試験は、局のお偉いさんや、ニュースキャスターにずらりと囲まれ、質問を浴びせられるという形式だった。俺は、何を訊かれても、すらすらと返答出来たと思う。これよりももっと大勢の前で講義することが日常なのだ。たかだか10人やそこらの前に出て、あがることなど考えられない。
それから二週間後。俺が受け取ったのは落選通知だった。
約束通り、アリスの夕食の支度をしながら、俺は納得いかない、と繰り返した。
「他に来てた奴らよりも、俺のが絶対カメラ写りだって良かったはずだし、ものを喋るのだって、慣れてた。片手間でやってやろうなんて甘い考えが見透かされたのだとしたら、テレビ局の奴らも侮れない。けど、どうも向こうは、そんなことにはあまりこだわっちゃいない様子だったんだぜ」
休憩だと言って、キッチンでお茶を飲んでいるアリスが首を傾げる。
「ほんまに落とされた理由解らへんか?」
「しいて言うなら、独身だからかな。お堅いニュース番組のレポーターに、スキャンダルは困るだろう。俺みたいにいかにももてそうな独身の奴を起用するのは危険だとでも思われたんじゃねぇかな」
俺は、自分でもあまり説得力の感じられない理由を言ってみた。
「まさか、それは逆やないか。既婚者でもてそうなら、そういう危険も考えるやろうけど、独身やったら誰かと噂がたっても、スキャンダルやないんやから」
言われてみればその通りだった。
俺が言葉に詰まると、アリスはとても楽しそうに言ってくれた。
「さすがの名探偵も、自分のことは推理出来へんてことなんやな」
「おまえには解るってのか?」
「当然やろ。そうやなかったら、こんな賭けをしようなんて、言わんかった」
俺は野菜を刻む手を止めて振り返る。
「何が敗因だって?」
「先生のは慣れ過ぎなんや。どこへ出ても堂々としてい過ぎるんや。テレビ局で募集かけたのは、もっと素人くさくて、純朴そうな男。いかにも、大手企業を蹴ってでも、第二の人生に賭けてるって感じのする人物や。おまえみたいに、誰の前でも不貞不貞しいのはいらんやろな。嘘から出た実やなくて、身から出た錆やったってわけや」
随分な言われようだが、仕方ない。言われてみれば、まったくその通りなんだろう。
「まぁ、ええやないか。おかげで一週間、毎日会える。俺はテレビ局に感謝しとるよ」
「便利なコックがただで調達出来て?」
「そんな卑屈な言い方せんでもええやん」
アリスはそう言って、空のカップを手に流しの脇にいる俺の横に並ぶ。にっこりと笑うと少し背伸びして、俺の唇をアリスのそれがそっとふさぐ。
野菜と包丁で両手がふさがっている俺は、おとなしくそのキスを受け取った。俺も少しだけ、テレビ局に感謝してもいいかな、なんて考えながら。
〈了〉
ショートショートの目次に戻る
TOPへ戻る