● 何故、ここでストロボの紹介?
それは、Web Masterの本職が商業カメラマン(カッコ良く言うとフォトグラファー)で、ストロボを日常的に使用しているからです。こんなところにも電気の知識が役立ちました。
● 一寸、古い設計ですが!
91年、設計・製作です。実はこのストロボジェネレータ、9作目(種類として)でこれ以降、新たな製作を行なっていません。しかし、現在でも実用性は十分で、性能は安定しています。ちなみにもっと古いタイプ(81年製造)もまだ現役で頑張っています。故障も殆どなく、30台ほど製作した中で、修理として戻って来たのは2台だけで、その1台は使用者のミスによるものでした。信頼性は充分なもので譲り渡したカメラマンには感謝されております。
本機はWeb Masterの全くのオリジナル設計です。製作を思い立った当時(75年頃)、国産品にはまともな製品がなく、手本になるとは思えなかった。コマーシャルの分野ではバルカー(アメリカ製)がよくレンタルされていた。しかし、このバルカーもやたらに大型で故障が多かった(暗い所で内部を覗くと待機中の電圧制御動作でリレーから青白い火花が発生しており、火花を発生させる構造では故障が多くて当然と感じた)。
ストロボの業界は電子技術が未熟だな〜と感じていたが、自分も全くの未経験の分野で、電力制御素子に何を使用したら良いか分からなかった。そこで、懇意にしている半導体屋さんに相談したところ、サイリスタなるもののヒントを得たのでした。それからはサイリスタについて猛勉強をし、各種の試験で耐性の実感を得て壊れないストロボを得ることが出来ました。制御素子がトライアックでなく、双方向接続のサイリスタであり、このサイリスタの制御を矩形波に整形した鋭いパルスで駆動しているあたりがミソです。
壊れないストロボとは回路設計に余裕を持たせるだけではなく、回路の構造を実装するテクニックに大きく影響します。その留意すべきところは、高電圧・大電流部分や、高電圧回路と低電圧回路の分離、放熱の工夫などです。
● 製作される方へ
本機は、高電圧・高容量コンデンサー(650V/7000μF)を動力にして、キセノン管を発光させます。その電流は瞬間的に、1000Aを越える場合もあり、高電圧の絶縁工作技術と、大電流の接続工作技術が必要です。(これを上手くやらないと、故障の多いストロボになります。)
また、感電やショートした場合、重大事故に至ることも考えられます。十分注意して下さい。(本機のグランドはケースにアースしないで下さい)
発光部は入力2000Ws以上のもので、石英ガラス製の放電管を装備したメーカー製をお薦めます。
なお、当方は本機の製作によって生じた、一切のトラブルについて、その責任を担保しません。
● ストロボの心臓部「充電/放電制御」
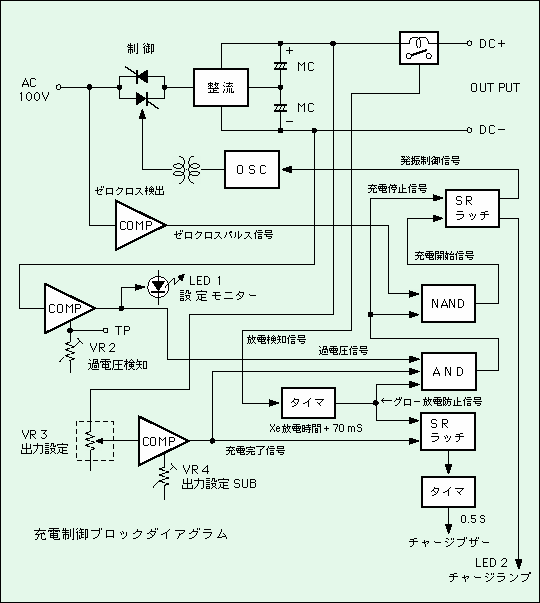
上図は、制御部のブロックダイアグラム図です。簡単に説明しましょう
■ 充電は負側コンデンサーから開始し、正側コンデンサーで停止完了します。その時、入力電源のゼロボルト付近から充電を開始します。こうすることによって、正負両コンデンサーをバランス良く充電でき、制御サイリスタやコンデンサーにストレスを与えません。
■ 出力をコントロールするための設定電圧を検知するのは、正側のみで行なっています。だが、このような方法の場合、なんらかのトラブルで正側コンデンサーの充電がスムーズに行なわれない時、負側コンデンサーの充電は進行しますので過充電になる可能性があります。これを防止するために、負側に過電圧検知システムを設け、コンデンサー保護に万全を期しています。(この安全装置、未だに動作した事がない)
■ 放電(発光)開始したら一次側からの電源供給を停止しなければなりません。これをしないと、グロー放電と言って連続発光状態になってしまいます。
放電状態を監視するために、放電経路中に2〜3ターンのコイルを作り、その中にリードスイッチを組み込みます(リードリレー構造)。そのスイッチは放電が終止するまでON状態を持続します(約1/30秒)。つまり、この時間の間、充電を休止しています。
放電管の種類によっては(連続発光などのオーバーヒートに弱いもの)、放電終止直後に充電を開始すると再び発光して、マルチストロボ(間欠発光)状態になる場合があり、それを防ぐために放電終止からさらに約1/15秒間、充電休止状態を追加持続します。