河口域の塩分濃度
|
既知の濃度の食塩水を使って比重を測定した結果が右の図です。2種の機差は小さく、同じように使えそうですので、AngelTestを主に使用しました。 ただし、AngelTestでも低濃度域の測定にはちょっと無理がありました。例えば理論的には真水 で比重1になるべきところが、塩濃度1%ですでに比重約1となりました。 →低濃度域の値に怪しい所がありますが、安物なので仕方ないところです。以下、比重から求めた塩分濃度にて考察を行っています。 2.測定結果
(1)定点測定 河口付近の同じ場所で満潮前後の塩分濃度変化を測定しました。測定時の気象条件は以下の4通りです。
・凪①、②:海は静かで、川の水量は少なめ。 普通の条件(凪①、②)の場合、上げ潮から満潮前後までは塩分濃度3%前後で推移し、これは外洋の塩分濃度(3.3-3.5%)よりやや薄い程度です。しかし満潮後60分経過すると塩分濃度 は2%以下まで急激に低下しました。上げ潮に押されて流れ出なくなった川の水が、下げ潮で急に流れ出たための変化と推測されます。 雨の日は川の水量が多いので、上げ潮時でも2-2.3%程度と塩分濃度が薄い状態で推移し、満潮を過ぎると急激に塩分濃度が低下しました。 荒れの日は満潮までは塩分濃度が3.5%と外洋とほぼ同じ濃度で、満潮後2時間でも塩分濃度3%を維持していました。波と一緒に沖の海水が河口に押し寄せるため高い塩分濃度を維持していると推測されます。
|
次に河口部分から100m位?川の内側まで測定場所を変えて塩分濃度を測定しました。 気象条件:凪で川の水量は少ない。中潮
尚、満潮2時間前のデータのみは測定日が異なります。 3.クロダイの行動パターン 河口でのクロダイの釣果は満潮後1時間までが多く、雨の日は満潮までが多いようです。
この経験則と今回の測定結果を基にクロダイの習性を推測すると・・・
結論:クロダイが釣れる目安は塩分濃度2%以上!? 川の大きさや水量で塩分濃度の変動は違うでしょうし、流れの中心と岸寄りでも塩分濃度は違うと思われるので結論はあくまで目安です。実際、塩分濃度1.3%でも釣れた場合もありました。 結論の真贋はさておき、比重計は海の状況を判断する道具として使えそうです。
|
 時々、河口でクロダイ釣りをすることがあります。さらに最近は近所の河口にカニ捕りにも出かけています。潮の干満により河口域の塩分濃度がどの程度変化するか、比重計を用いて測定してみました。
目的はクロダイが釣れる塩分濃度範囲の目安を掴むことです。
時々、河口でクロダイ釣りをすることがあります。さらに最近は近所の河口にカニ捕りにも出かけています。潮の干満により河口域の塩分濃度がどの程度変化するか、比重計を用いて測定してみました。
目的はクロダイが釣れる塩分濃度範囲の目安を掴むことです。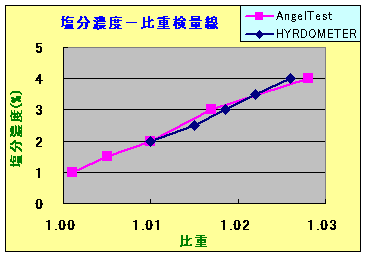 1.測定精度の確認
1.測定精度の確認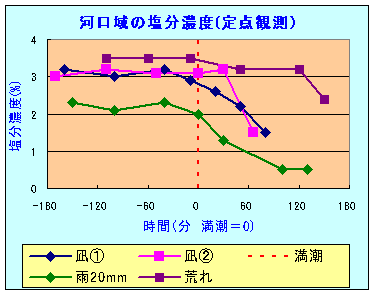
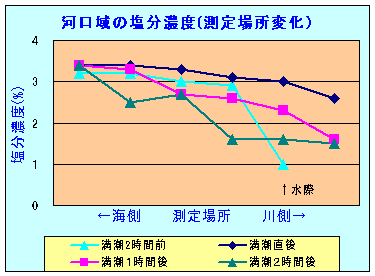 (2)測定場所変化
(2)測定場所変化