● 仕掛けと当たりの出方
釣り人が一番悩むのは仕掛け。
円錐浮きか棒浮きか、 浮きは重いものか軽いものか、 ガン玉は重くするか軽くするか、 ハリスは長くするか短くするか、
完全フカセか スルスルか、 はたまた沈め釣りか・・・・・・・・・・・・
釣り雑誌やフィールドテスタなどのHow toものを元に、
人それぞれにいろいろな思惑で自分なりの仕掛けで釣りを楽しんでいます。
それぞれの釣り方で利点欠点があるのだから、 それぞれの好みで楽しめばいい。
しかし、
いわゆる仕掛けのなりと当たりの出方に関して、皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか?
私の持っているイメージを提示することによって、これを読む方々の何かの役に立てればと思います。 もちろん私のイメージが100%正しいとは思っていなし、一般に言われていることもどんな名士のいうことであれ100%正しいとも思ってはいません。 どちらも、裏づけのないスケッチです。 想像することがどれだけ現実に近いかは、これを読む皆さんが判断なさることです。
さて、 皆さんの持たれるイメー ジと どう違うでしょうか?
下手なスケッチで説明がちょっとくどいですが、ご容赦ください。
説明の都合上、 全体を通して理解しやすくするために、
最初にもっとも単純な 完全誘導・完全フカセの場合から始める。
■当たりの出方・・・・・完全誘導・完全フカセ(スルスル)の場合
スルスル釣りで針・餌の自重で沈んで行き、浮きにブレーキをかけながら流していると、
仕掛けは放物線を描き、餌付近はより垂直近くに立っている。
浮きのすぐ下の道糸はほぼ水平近くに横を向いている。
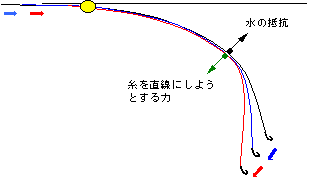 |
魚が餌を咥え(黒)、 左下に移動すると(青→赤)、 この場合、浮きを下向きに沈める力はほとんど発生しない。浮きが沈むのは 仕掛けがより立っている場合である。 だから、この釣り方では、浮きで当たりを取るのではなく、道糸の走りで当たりを取ることになる。 |
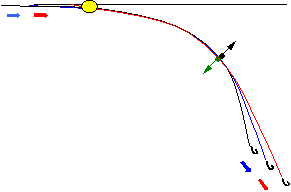 |
魚が餌を咥えて右下に移動した場合の図である。 釣り糸の長手方向に魚が動くのでより当たりが出やすい。 実は、スルスル釣りの最大の利点はこの点にある。
|
■当たりの出方・・・・・完全フカセの場合(浮き止めがある場合)
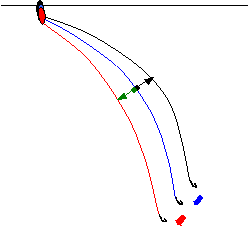 |
まず魚が餌を咥えて左下に移動した場合で考えると、 スルスルの場合と異なり、 道糸がフリーではないので、 糸の接線方向の動きは浮きを引っ張る力になる。 針と浮きとの引きあう力で浮き下はより直線に近づくように移動していく。 そして、同時に浮きは接線方向の力で僅かに沈む。 ここでの浮きを沈める力は直線の糸で直接的に引っ張られるものとは全く異なるものである。 私がこれまでのScrapsで触れている “潮の横抵抗によるシモリ”のことである。 つまり、 糸の接線方向の力が浮きの残存浮力と釣りあった状態になる。 “仕掛けに関するあれこれ” で触れたように、約7m/分の流速で 1mの1.5号ハリスは45°たなびき、 これを垂直にするには2号程度の重さ=0.37grが必要になる。2mなら0.74grである。 想像以上に糸の潮抵抗は大きいのである。 スルスルでは道糸がフリーなのでこのシモリは出ない。 |
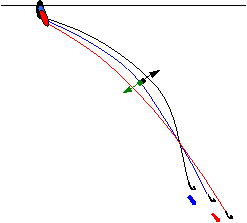 |
魚が餌を咥えて右下に移動すると、 糸の長手方向に魚が引くので、接線方向への力の割合が増えてくる。 このように、 糸が直線になる前の浮きの変化が、黒鯛釣りでは非常に重要になる。 感度のいい浮きが必要なことは言うまでもない。 |
<ここまでのところでの補足説明>
- 糸が水から横抵抗を受けたとき、道糸が接線方向走ることは、たとえば風などの影響から表面流で膨らんだ道糸を修正しようと引っ張ると、 道糸がまっすぐなる前に浮きは道糸の膨らみをなぞるように動いてしまうことから、容易に想像できるだろう。
- 潮の横抵抗は魚の移動速度に大きく関係している。 その断面積に比例するが、速度には2乗に比例する。
完全フカセでいえば、移動が極端に早い場合は糸の膨らみはそのままに 浮きが消しこまれていく。
あるいは鋭い合わせを入れれば、糸が浮くらんでいても針がかりさせられるのも、同じ原理によるものである。
逆に遅い場合は、横抵抗が小さいので、 ゆっくりと糸が直線に近づいていき、 当たりはほとんど出ない。
この意味で、動きの遅い黒鯛釣りではあまり良い釣法とはいえないが、食い込みのよさとのTrade offとなるだろう。
- また、食い込みに関していえば、
”完全フカセで何も付けていないので、魚が感じる抵抗はなにもないので良く釣れるのだ”
という話をよく耳にする。 しかし、海中では、道糸ハリスは上述のような横抵抗や粘性抵抗を受けているのであり、この考え方は大いに疑問である。 いや、間違いである。
- スルスルに関しては、黒鯛の感じる負荷が糸の粘性抵抗だけで、 あらゆる浮き釣法の中では黒鯛が感じる負荷はもっとも小さい。 この意味では優れた釣法だろう。 ただし、実際どの程度 差があるかは疑問である。
そもそも黒鯛が餌を口にしたとき、わずか0.2〜0.6grの負荷で不自然に引っ張られる間隔がどの程度影響しているだろうか。
むしろ スルスルや完全フカセでの効果は餌の流れ方や落ち方がより自然である、という観点で捉えるべきだろう。
ここでの本題とは離れるのでここでは深入りしない。
■当たりの出方の違い ・・・・・・外錘の重い/軽い、 完全フカセとの差
次により一般的な仕掛けの場合で考えて見る。
浮き下には外錘(浮力調整用)を付けて、その下にハリスを適当な長さでなびかせる釣り方の場合である。
完全フカセとの違いは、浮き下の釣り糸の膨らみ方が異なってくるので、 当たりの出方が違ってくる。
まず、スケッチを描く前の仮定として、
- 仕掛けが斜めになびいている場合を想定する。
潮どまりや、 上下層で潮速が一定ならどんな仕掛けでも垂直に立っているので検証する意味あいはあまりないからである。
- とりあえず、 浮きは円錐浮きと棒浮きの中間的な特性のものとする。
- 餌の加えた魚が就餌後、動く方向を4種類(左右、 左右の斜め下)で比較してみる。
- 外錘 :重い → 0.5〜1号程度の重い外錘を想定。
- 外錘 :軽い → B〜4B 程度の軽い外錘を想定。
- 完全フカセ → 外錘なし。
- 針チモトにガン玉5〜7号を打ってるものとする。
- 比較のため、 浮き自重+外錘の総重量は同じとする。
- タナは竿1本ほどを想定。
|
1)魚の引く方向 : 右斜め下
a)外錘:重い b)外錘:軽い c)完全フカセ 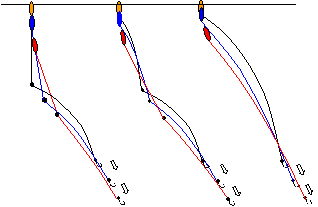 |
c) b) a) a)〜c)を比較すると図から分かるように、黒鯛の移動量に対する浮きの変化量はa)が一番大きく、 いわゆる感度という点では一番高いといえる。 当たりの出やすさ・大きさは a>b>c |
|
2)魚の引く方向 : 左斜め下 a)外錘:重い b)外錘:軽い c)完全フカセ 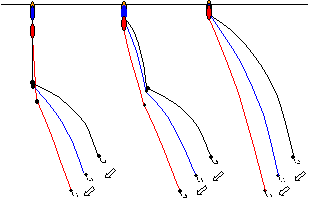 |
左斜め下の場合は、 糸が直線に近づくのは 1)右斜め下の場合より遅れる。 潮の横抵抗の割合が大きいので、いわゆるシモリの期間が長く、 浮き入りは 1)の場合より遅れ、ストロークも短い。 a)〜c)を比較すれば、やはりa)が最もはやく、大きく、浮き入りする。 当たりの出やすさ・大きさは
|
|
3)魚の引く方向 : 左 a)外錘:重い b)外錘:軽い c)完全フカセ 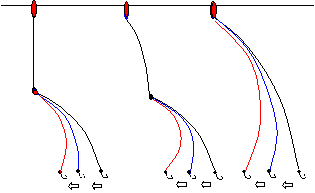 |
魚が左に移動した場合、 道糸ハリスが膨らむ方向であるため、どの場合も当たりは非常に小さい。 この場合は浮きを引く力は、 潮の横抵抗だけである、釣り糸の接線方向の弱い力だけである。 当たりの出やすさ・大きさは
|
|
4)魚の引く方向 : 右 a)外錘:重い b)外錘:軽い c)完全フカセ 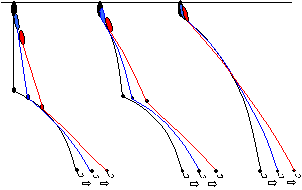 |
魚が右に走ったときは、 1)の状態に近いが、1)と比較すると、下向きの力成分が小さい。 だから、糸が直線になる前のシモリの量も1)より小さく、直線になった後の浮き入りの量も1)より小さい。
当たりの出やすさ・大きさは
|
このスケッチから、要点を整理すると、
- 外錘はより重ほど、当たりは出やすい (浮きと外錘の総重量が一定とした場合)。
- 完全フカセは、もっとも当たりが出にくい。
- 糸の膨らみを増長する方向へ魚が動いた場合は、どんな仕掛けを使っても当たりは取りにくい。
<補足>
- 潮の流れがなく底を釣っている場合、仕掛けは垂直に立っているが、 黒鯛は底を横にしか移動できない。
だから、実は、この場合の当たりの出方は ここまで何度も説明している潮の横抵抗によるシモリがほとんどなのである。
これは、底を這わせるような釣り方、 団子釣りのように垂直に仕掛けが立つ場合など、 全て共通していえることである。
- ここでの当たりの出方の違いは、タナが深いほど顕著になる。 糸の膨らみはタナが深いほど大きく、 糸が直線になるまでその分時間が掛かる。 そして、仕掛けが直線的に引かれることよりも、上記の糸の横抵抗の割合が大きくなってくる。 タナが深いほど、当たりがヌメっとしてくるのはこのためである。
そして、タナが深いほど、外錘が重いほど、当たりは鮮明に出るようになる。 極端な話、 船釣りや投げ釣りで50mも先の魚信をとるのに、 何10grも錘で糸を張らないと魚信が取れないないのと、よく似た話である。
- 大雑把にいえることは、
タナが浅いほど、 完全フカセが有効。
(浮き下が短い分、 糸の膨らみが小さいから、直接的な当たりがでやすい)
タナが浅いほど、 浮き・外錘は軽く感度の良いものを選ぶ。 浮きの残存浮力も小さく抑える。
(浮き下が短い分、糸の受ける横抵抗が小さいから、高感度化が必要)
タナが深いほど、 あたりを取りやすくするため外錘は重くした方がよい。 残存浮力も大きくする。
(糸の潮抵抗に負けないようにするため。 残存浮力が小さいと潮の動きで浮きが沈んでしまう)
外錘が軽いほど、浮きは軽く感度の良いものを使う必要がある。 いわゆるバランスの問題。
(直線的に引っ張られる割合が減ってくるので、 糸の横抵抗→接線方向の動きを検出できるように)また、潮が早い遅いの場合も同様なことがあるが、 もう説明するまでもないだろう。
■円錐浮きと棒浮きの違い
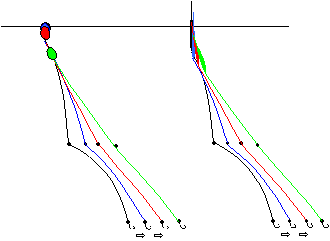 |
円錐浮きと棒浮きのあたりの出方を比較してみる。 もっとも違いが顕著なのは、糸は直線(緑)になる前の当たりの出方である。 したがって、良く言われるように、円錐浮きの場合は仕掛けをなるべく直線的になるように段シズなどを打つ必要性がでてくる。 ただし、このような処置をしたからといって、左下方向に魚が動けば何の意味もない。 逆に棒浮きは潮に揉まれたとき、浮きがシモリやすい。 潮の横抵抗に耐えられないのである。 このような観点からみれば、円錐浮きはよりアタリが直接的に出やすい浅場、浅タナ向きの浮きと言えるだろう。
|
<補足: 水中浮きについて>
水中浮きの役割について、普及している割にはその効用の捉えた方がまちまちである。
よく分からないで使っている人も多いのではないだろうか。
その効用について、ここまでをじっくり見て頂いた方はもうお分かりだと思う。円錐浮きでは軽いガン玉が使われることが多く、糸が膨らみやすい。 上潮底潮の差が大きくなるほど顕著になる。
これまでの説明で触れたように、糸が膨らんでいると円錐浮きはアタリが取りにくい。 しかし、水中浮きをセットすると、水中浮きは体積が大きいので潮抵抗が大きく、上浮きと水中浮きが引き合う。
この引き合う力で浮きと水中浮きの間の糸が直線状に張る。 つまり、糸の膨らみが取れてあたりが取りやすくなるのである。 また、 前例の外錘が重い場合と同様に、 魚が引く力が水中浮きに伝わると、この力が直接的に上の浮きに伝わるため、さらに当たりが取りやすくなるのである。 いわば 円錐浮きの欠点を補う小道具ともいえるものである。効用 について他にもいろいろあるだろうが、 ここのテーマから見た最大の効用は上記の点である。
この点で、糸が膨らんでいても当たりが取れる棒浮きの場合は、円錐の併用はあまり意味のないものになる。
<補足: 重い棒浮きと軽い棒浮き>
糸が直線になる前に発生するシモリの状態というのは、 黒鯛の移動が極めてゆっくりな場合は、浮きの残存浮力と潮の横抵抗とが平衡する状態に近い。 だから実は、Topの沈む量は 浮きの重さに余り関係していない。 この点はあまり気付かれていないと思う。 もちろん、動的に考えれば、重い方が慣性が大きいので動きにくくなるのは当然である。 しかし、黒鯛特有のジワーっとした超のろまの変化では加速度が小さいのでほとんど影響はしていないと場合が多い。
どっしりとした浮きを使っても Topのわずかな変化で当たりが取れるのはこのためでもある。
■短ハリスと長ハリス
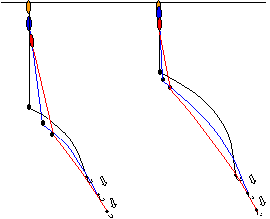 |
次に、ハリスの長短での当たりの出方の違いを見てみる。 長ハリスでは、ハリスの膨らみが大きいので、 潮の横抵抗→シモリの期間が長く、 直接的な当たりが出てからの浮き入りのストロークも小さい。 短ハリスでは、逆に、ハリスの膨らみが小さいのでシモリの期間が短く、 浮き入りのストロークも大きい。
|
以上、 いかがでしたでしょうか?