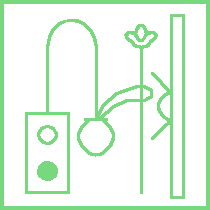|
デンデラのハトホル神殿は、南の外壁のクレオパトラ(紀元前51-30)と、彼女の息子カエサリオンの像で有名である。 もうひとつこの神殿の名を有名にしているものがある。 黄道十二宮図である。 この十二宮図では、黄道にそって36の星座が描かれている。 十二に分割したのは、バビロニア起源らしいが、この36分割、ギリシア語でいうところの「デカン(十分角)」-360度の天を10度づつ36分割-の採用は、エジプト人の功績とみて良いと言われる。 デンデラの図では、獅子座、やぎ座、双子座、牡牛座等が現在の十二宮と共通した姿で描かれている。

デンデラ ハトホル神殿の十二宮の図
ところで、この天体図の中央にある牛の腿や、河馬等が、先に述べた北の空のエジプト固有の星座である。 牛の腿は、現在の、我々のいうところの北斗七星(大熊座)にあたり、これは、セトの腿とされる。 そして腿(セト)は雌河馬の姿をしたイシスによって、2本の杭につながれて、オシリス(オリオン座:図の右下の円の中の人物)より南の空(オシリスによって生み出された神々がいる空)に行かない様にされているという。 もっとも、通常、オシリスに対するイシスと見られる星は、シリウス(おおいぬ座のα星、全天で一番明るい星、この図ではオリオン座の後方の牛の角の間の星)であろう。(注:本来、シリウス星はソティス女神、オリオン座はサフと呼ばれる神とされたが、オシリス神話と結びついて次第に、オリオン=オシリス、ソティス=イシスと見られる様になっていた様である。) また、牛の腿は、先に見た王家の谷のセティ1世の墓の天
体図や、ハトシェプスト神殿近くのセネンムトの墓の天体図等では、牛の姿で表されている。
また、北斗七星は、ミイラに死後の生を与える儀式、”口開けの儀式”で使われる『手斧』にも見立てられることもあった。 この場合、大熊座(北斗七星)、小熊座の二つの星座が、二つの手斧と呼ばれた。
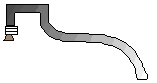 |
| 開口の儀式に用いられた手斧 |
| 

 GO
GO